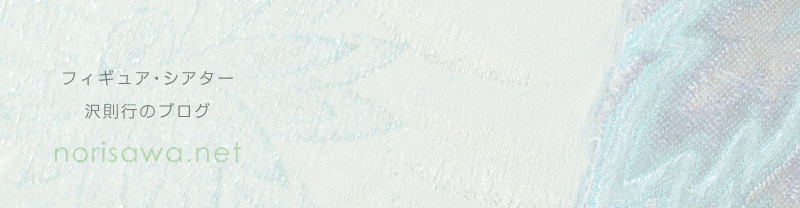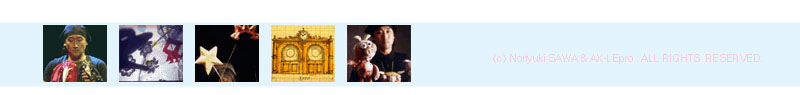ドラマツルグ、って何?
[2009.11.04] [「児童演劇」原稿]
児童演劇06年11月号原稿より
以前にも書いたが、演出家や美術家と並んで、「ドラマツルグ」という役割が、
チェコの芝居づくりではとても重要だ。
たとえば次の新作には赤ずきんをやろう、とプロデューサが言い出したとする。
そのとき、ドラマツルグは、うちの劇団が、なぜ、今、どのようなスタイルで、
またどのようなねらいで作品を作るのか、場合によってはキャスティングや
宣伝方法まで含めて、責任をもって他のスタッフと討論して決定してゆく。
赤ずきんが迷い込む森は、彼女自身の心の中なのではないか、
いや、狼こそ森そのものだろう、ならば、狼も赤ずきんの一部だと
する設定はどうだろう、赤ずきんは自分自身の心の暗がりを通り抜けることによって、
大人の女性へと成長することになる。さてこれは現代社会に生きる少女たちにとって、
どんな意味があるのだろう?
舞台装置は少女の白いドレスを巨大化した図案、
それがトンネルのように開くとしたらどうだろう、
そのトンネルは狼の口のようにも見え、ときに閉じてしまう、というのはいかがか。
では肝心の役者たちはどんな位置づけにするか。
森の精? それでは陳腐だ。
木や葉っぱ、土くれといった森の「部品」ならば面白いかも。
いっそ、全員、狼ではどうか?
いずれにしても少女は、彼女をとりまく社会環境に、
明るく、コケティッシュに挑んでゆく、そんなお話にしたい。
ならば音楽のテイストは? 前作のシンデレラとのつながりは?
国外のフェスティヴァルでもグリムが多く演じられているが、それらとの差別化は?
ドラマツルグは脚本家を兼ねることもあるが、
基本的に上演と劇団活動に指針を与える役目だ。
必然性と枠組みとも言える。
だから、芝居づくりのみならず、フェスティヴァルにも、
イヴェントにも、すべての創作活動にドラマツルグが必要となる。
もしも、この役目がいないとどうなるだろうか?。
おそらく、プロデューサと演出家、または劇団代表が、
経済性と自分の思い入れのハザマで、妥協点を探して遺恨試合を
繰り広げることになる(大袈裟だ)。
ここまで読んで、いやそれは日本では劇団代表の仕事、演出家の仕事、
プロデューサの仕事、または芸術監督の仕事、と分担されておこなわれている、
と思われる方も多いだろう。説明がむずかしいのだが、ドラマツルグとは、
それらのハードとソフトづくりに一貫したストーリィ性を持たせる役目、と言える。
劇団や劇場が、その国の歴史の中で、ある固有のテイストを保ち、
他劇団と差別化しながらも、永く共存してゆくための、独自の「匂い」を作る役目、
どこまでも客観的なひとつの「目」だという感じがする。
説明がさらに抽象的になってしまって申し訳ない。
ぼくは、予算が保障され、スタッフも出演者もすばらしいのに、
ドラマツルグが馬鹿なばっかりに、無残に失敗した芝居や
フェスティヴァルをいくつか知っている。
差しさわりがあるので、具体名は挙げられないが、あるダンスの一分野に、
多くの社会主義国で、かなり手厚く保護された芸能の一ジャンルがある。
すべての旧東欧諸国が自由化された現在も、いくつかの国立芸術大学の中に
それは学科として存在する。
しかし、分野としては新しい方向性を強く打ち出せないまま、
かなりの速度で衰退している、と言わざるを得ない。
先日、その学科の教授たちが、学生たちとともに舞台に立ち
、デモンストレイション的なワンナイト・フェスティヴァルを開いた。
教授陣の古典的なテクニックに加え、何とか分野を外に開こうとする
学生たちの新しい肉体的挑戦が見られて、終盤までとても刺激的な構成だった。
しかし、最後の最後で、出演者全員がストロボライトの中に踊り出て、
コミカルに動き回り、通常の照明に戻ったときに皆で手をつないでカーテンコールする、
というとんでもないアナクロ・エンディングを見せて、
企画全体を台無しにしてしまったのである。
そこでぼくが感じたのは、かつては、ひとりひとりのベテラン・ダンサーが
ピンで観客席をいっぱいにできたはずなのだが、
今は学生も引き連れて舞台に立たなければならない現状。
そして、詩的でアヴァンギャルドな演技を見せたその学生たちが、
とても恥ずかしそうにそのエンディングに耐えている姿、だった。
これは明らかにドラマツルグの失敗である。
その芸能の時代性、未来に向けてどう変わって、何を訴えてゆける分野なのか、
その夜のフェスティヴァルの意図は、と熟考したときに、
たとえ学科長が提案したアイディアであっても、このエンディングはあり得ない、
と評価すべきなのがドラマツルグのはずなのだ。
つづく
「チェコの古典人形劇でも、ドラマツルグは重要」
芸術大学の演劇教育(後編)
[2009.10.27] [「児童演劇」原稿]
児童演劇2005.11月号原稿
大学での仕事について続きを。

グループワークを主体にカリキュラムを進めると、やがて学生たちは各々の内面を
反映させられる課題や、詳細な表現技術を個人的に求めるレベルに到達する。
そこで今年、二年生の授業でかなり危険とも思える、
しかし一度はやってみたかったプログラムを試している。
まず、ひとりひとりに紙を配り、今、あるいは今までの人生でもっとも大きな問題、
つらかった悩みを、無記名で書いてもらう。
それらを大きなポリバケツに集め、シャッフルした上で各人がくじ引きのように選び取る。
そして内容を読み上げる(日本のプロ野球のドラフトを思い出してみて欲しい。
ただし、紙を手にした者の表情は、球団監督のそれよりかなり暗く、笑顔も深い)。
とてもプライヴェイトな内容なので、ここで詳しく書くわけにはいかないが、
家族のこと、自分のこと、性のこと、人間関係などなど、十一人分の内容を
読み上げたときには、全員がグッタリしてしまった。
彼らの課題は、自分が手にした誰かの「大問題」をモチーフに、一人芝居を作ることなのだ。
この学年は入学当初からとても明るく、協調性も高かった。
今回驚いたのは「自分はとても孤独だ、自分には一生友だちはできないような気がする」
といった内容がいくつもあったことで、青年期の典型的な自意識であるとともに、
人の心の深みに分け入って、それを表現できる一流の役者となるためには、
絶好の訓練チャンス。
家族関係に深い問題を抱えるケースにあたってしまったある学生は、
今、以下のようなスケッチ稽古を繰り返している。
そっと食卓の上に粘土を置き、それをゆっくりこね始める。
やがて粘土でもうひとつの食卓ができあがり、父が、母が、
そして本人である息子が練り上げられる。
さらに食卓の上には粘土の食器や夕食が並び、三人は夕餉を始める。
やがて父親の粘土人形がけいれんし、おおきく膨らみだし、食卓全部におおいかぶさる。
母と息子はもがきながら巻き込まれる。
混乱の後、再び素材としての粘土に戻る食卓。
それはひとつの顔、悲しい仮面になっている。
都会での集団生活に適応できずに苦しんでいる、というケース。
小さなロウソクが一本、大きなロウソクの集団の中に入り込む。
しかしその光は大勢の中であまりに非力で、輝きを失ってしまう。
逃れた小さなロウソクはみずからカップをかぶり、そのともしびを消してしまう、
あるいは透明なガラスに守られたランプケースの中に入り込み、
火は守られるものの、外の世界の風を感じることはもうない。
その学生はラストシーンをどうするかで試行錯誤中。
そう、扱っているテーマがそれぞれ重いので、表現内容もかなり重い。
しかしすぐれた芸術作品に必ず兼ね備わっているとされる四つの条件=美しさ、
スタイル、統一性、そして軽やかさ。これらを忘れずに創造を続ける必要がある。
もうひとつの受け持ち学年は三年生。
今学期はシェイクピアの「夏の夜の夢」が課題だ。
昨年はチェホフの「桜の園」に挑戦したこのクラス、
古典をきちんとこなせる演技力を身につけようと必死だ。
「桜の園」では人形は一場面だけ一体のみ、「夏の夜の‥」
ではまったく人形が登場しない。
しかし会話の途中、登場人物すべてがふと舞台隅に目をやる、
ああ、見慣れた森の妖精だ、という表情ですぐに会話に戻る、といった演出で、
その世界にあるべき幻を観客の心に想起させるメソッドを取る。
その一瞬の間(ま)こそがこの作品で使われる人形となる。
国立芸大の授業料は基本的にタダ。
つまり国が税金で面倒を見る。
しかし、入れば何とか出られる日本のシステムとは異なり、
ヨーロッパの進級と卒業はかなりたいへんだ。
努力の見られない学生、努力していても到達度を
クリアできない学生は容赦なく切られ、退学となる。
最終学年は、プラハ市内の劇場に丁稚奉公のように出され、現場で揉まれる修行の一年、
あるいは学年から選抜されたアンサンブルで国内外のフェスティヴァルに出まくり、
思いっきりきたえられる、という場合もある。
入学したらすぐにでもプロの現場に照準を合わせていない学生は、業界で使えない。
ただ、今のところ、放っておいても彼らは入学当初から何かしら自主的に創作し、
正規の授業に差し障りがあるからやめろと云われない限り、
小劇場での自主公演を常に繰り返している。
見あげた根性だ。
つづく
「大学の授業風景、影絵をためす学生たち」
児童演劇 2005年10月号掲載原稿
[2009.10.19] [「児童演劇」原稿]
児童演劇 2005年10月号掲載記事
芸術大学の演劇教育(前編)
プラハには国立表現芸術アカデミーという大学がある。
正式名称はアカデミエ・ムージツキーフ・ウムニェニーと云って、頭文字を取って
通称アムー(AMU)と呼ばれる。ちなみに、絵画や工芸といった造形芸術には
また別のアカデミーが存在する。さて、アムーには映像、音楽、舞台の三学部があり、
それぞれフィルムのエフ(F)をくっつけてファムー(FAMU)、チェコ語で音楽を
意味するフドバのエイチ(H)でハムー(HAMU)、舞台芸術のディヴァドロのディー(D)
からダムー(DAMU)と呼ばれている。
舞台学部ダムーには二つの学科があり、ひとつは一般的な演劇学科、
もうひとつは演劇・人形劇学科とでも呼べば良いのだろうか、
もともと古典的な人形劇から出発しながら、いわゆる「何でもあり」に進化した
現代のフィギュア・シアター専攻の学科である。ぼくはそこで講師として働いている。
この学科には俳優コース、人形・舞台美術コース、脚本・演出コース、
プロデュース・マネージメントコースなどがあり、四〜五年制、その後、
修士や博士課程もある。入学の競争倍率はスゴイ。ぼくが担当している俳優コース一年生は、
二百五十人あまりの受験生から選び抜かれた十一名だった。選抜は個人の実力だけではなく、
そのメンバーでアンサンブルを組んだ場合の集団としてのバランスや可能性を重視する。
一次試験では身体能力や発声、音感、朗読、人形やオブジェクトを遣っての寸劇など、
個人の基礎的資質が試されるが、二次試験では、創作グループとして共同作業する際の
コラボレイション能力が要求される。何人かの俳優志望の受験生に、演出コース、
美術コースからのメンバーも交えて、いくつかの即席劇団を編成し、同一の課題で短い
上演作品を作らせる。そしてそのグループワークの中で、きちんと自分のアイディアを述べ、
集団の中に溶け込ませ、活かしていけるキャラクターと力量が求められる。
つまりいくら演技や音楽的才能に恵まれていても、ひとりよがりで他との協調性が
なければ合格できない仕組みになっているのだ。
「説得力」は必ずしも「饒舌」を意味しない。皆さんも経験から良くお分かりのように、
会議で長ったらしく、大声で発言する人はけっきょく嫌われるのだ。

ぼくは授業でもよくグループワークをする。
あるとき、発言力の強い押せ押せのメンバーたちに遠慮して、なかなか自分の意見を
云い出せない学生ばかりを集めて別なグループを作り、インプロヴィゼイション
(短時間で即興も交えながら短い作品を創造する作業)を要求したことがあった。
受験を勝ち抜いたとはいっても、穏やかな性格のヤツはどこにでもいるし、
ましてや集団の中のキャラクター、役回りというのは、きわめて柔軟、相対的なもので、
超活発なメンバーを十人集めても、いつのまにかおとなしい人間が二割ぐらいは
できてしまうものだ。
で、目は底光りしているのに、なかなか自分の発想を言葉にできないそいつらを
一度集めてみたいとかねがね思っていた。
ぼくがあらかじめ与えたモノは、一本の懐中電灯と美しい日本の音楽一曲のみ。
テーマは自由。
空に浮かぶ大きな手からこぼれ落ちた光のしずく。
男は自分に落ちてきたそれをウザッタイ、とばかりに蹴り飛ばす。
蹴られた光は別の誰かに拾われ、やがて小銭のように物乞いに与えられる。
それを大切に胸にしまった物乞いは、やがて若い女性と出会い恋に落ちる。
彼らの口づけとともに光の玉は物乞いから女性の身体の中へ移る。
ゆっくりとふくらむ腹部。
やがて新しい命が女性の身体から生まれ出る。
赤ん坊を抱く幸せな母親。
再び空に舞い上がってゆく光の玉。
最初の男があらわれ、その光に気づき、つかまえようとするが、すでに届かない……。
彼らは壁に映る自分たちの身体の影だけを使い、二時間ちょっとでこの作品を創り上げた。
その作業の様子は、熱のこもった怪しい秘密会議のようでもあり、また、
子どもたちが懐中電灯を夢中になって取り合うゲームのようでもあった。
この短編は、やがて学期末の発表会で教授陣の感涙を誘い、
その後いくつかの国際フェスティヴァルで上演されることになる。
創ったときには想像もしない長い命を持った作品になった。
これはけっして指導者としてのぼくの実力ではなく、
彼らの「表現したい」という心の底からの思いが結晶した
素朴な宝石だったのだと思う。
つづく
「演劇・人形劇学科の入学試験」
こどもたちのカルチャー・キャンプ(後編)
[2008.06.16] [「児童演劇」原稿]
児童演劇 2005年7月号掲載記事
こどもたちのカルチャー・キャンプ(後編)
前回は、チェコのカルチャー・キャンプについて、ぼく自身が実施したサブジェクトから、カリキュラム全体の三分の二までを書いた。
その一、自由で新鮮な感覚で身体を動かすためのボディ・エクササイズについて。
その二、身のまわりのさまざまな素材を使って挑戦する人形浄瑠璃の三人遣いについて。
さて、今回はその三、いくつかのグループに分かれて実際に芝居を作るメインのパートについて、だ。
この段階で大活躍する機械が登場する。OHP(オーヴァ・ヘッド・プロジェクタ)と呼ばれる光学投影装置である。きわめて特殊なプロ仕様、ではない。皆さんも小学校などで見覚えがあるだろう、透明なプラスティク・シートにグラフや文字を書いて、デスク状のガラス面に載せ、下から透過する光を鏡に反射させてイメージを投影する、仕組みとしてはとてもシンプルな機材である(最近はデジタル・プロジェクタに押され、備品倉庫の片隅でホコリにまみれて眠っている…)。

「OHPを使って、森の赤ずきん」
森で子どもたちと拾った木の葉や木の実、透明なアクリル・ケースに満たした水や油、
カーテンのレースや、自分の手など。おおよそありとあらゆるモノをガラス面に載せ、
投影の効果を試してみる。子どもたちから歓声が上がる。
自分の手元にある小さな秘密基地から発信されるイメージが、
大きなスクリーンに映し出され、それらが動く不思議さと驚きが彼らをとらえる。
スクリーンは、大きな布地を広げたり、半透明のゴミ袋を切り開いてつなぎ合わせたり、
これも子どもたちとの共同作業で工夫して作ってゆく。
やがて、ただイメージを映すだけの影絵遊びから、スクリーンの前に立ち、
自分の体や人形に映像を映しこむ、さらに踏み込んでそれらのイメージと共演してみる、
などさまざまな演劇的冒険が始まる。始まらないときにはこっちからそそのかす。
この過程で重要なのは、綺麗な映像効果にただ振り回されてしまわずに、
人間が持つ身体表現の強さや、「劇人形」が持つ奇妙で深いクオリティを
しっかりと作品に加えてゆく、という作業だ。ステップ一のエクササイズや、
二の人形遣いトレイニングは、そのためにある。
例えばこんな作品があった。
舞台上に大きな野点傘(屋外で茶の湯を楽しむために使う、
あの大きな赤い傘。ぼくが日本から持ってきた)が開いておいてある。
傘の裏側で照明と切り絵を使った影絵が始まる。
子どもたちが小さな亀をいじめている様子。
ひとりの少年があらわれ亀を助けだす。
傘の表側にはOHPを使った水の映像が揺れ始め、裏側では亀に
またがった少年の影絵人形が、ふちの辺りからぐるぐる回りながら
中心軸へ向かって近づいてゆく。
ははあ、どうやらあのあたりに龍宮城があるらしい、と気づいたとたんに、
傘の裏から生身の役者たち、浦島太郎と乙姫が飛び出してくる。
すぐに「こんにちは」「ようこそ、太郎」とドラマは次の場面にジャンプする。
さっきまで海だった大傘が立ち上がり、乙姫の豪華な日除けに早がわりする。
チェコの子どもたちは、その日の朝に初めて聞いた日本の昔話を、
夕暮れまでにテンポの良い短編に仕上げた。
「三匹のこぶた」グループは、二本の柱の間に何往復も張り巡らせた
幅広の白いゴムバンドをスクリーン、また演技空間として使った。
こぶたたちが作るわらや木、レンガの家は、OHP上でティッシュペーパや枯れ枝、
また小石を家の形に並べてスクリーンに投射し、表現した。
これらの「即席建築」が便利なのは、舞台上の狼(人形ではなく生身の役者)が
スクリーンに息を吹きかける演技に合わせて、OHP係の裏方も実際に家を
ガラス面から吹き飛ばせる点にある。そしてお約束どおり、石の家は重いので飛ばない。
観客は狼の熱演とOHP係の奮闘、その両方を見ることができる。
家の中に隠れているこぶたたち(これは人形で、狼とのサイズ差が際立つ)は、
スクリーンのすき間から、次々と顔を出したり引っ込めたりして、狼を翻ろうする。
ゴムバンドの張力による素早い伸縮がそのスピード感を生んでいた。
カルチャー・キャンプの最終目的は共同生活の訓練ではなく、
その先にあるサブジェクトの達成だ。主催者は、その環境作り、
とりわけ子どもたちの健康管理に気を配る。
医師か看護士が常時滞在することが義務づけられているし、
栄養面からの配慮と、貴重な時間を自炊で浪費しないために、
専門の調理師(なぜかたいてい恰幅も気立ても良いおばさん)が付いて、
毎食チェコの田舎料理を提供してくれる。
こげたカレーで苦しんで稽古ができない、ということは起こらない。
さあ、今年ももうすぐ夏休みが来る。
つづく
こどもたちのカルチャー・キャンプ(前編)
[2007.05.22] [「児童演劇」原稿]
(児童演劇2005年6月号)
日本ではどうなのだろう?
チェコでは夏休みになると、山や湖で子どもたちを集めてカルチャー・キャンプがよく開かれる。
おとなと子どもが一定期間コテージやテントでともに生活し、何か一つのサブジェクト(科目)に取り組む。ぼくが毎年招かれているキャンプでは一週間ごとにサブジェクトが替わり、指導する講師も受講する子どもたちも入れ替わる。音楽やダンス、人形劇や英会話、山の鉱石を採掘したり、陶器を焼いたり。ただ歩く、というプログラムもあった。比較的若いスタッフ十人ほどが主催・運営しており、はじけまくる子どもたちや、デキの悪い講師のお世話係りも彼らがつとめる。
募集する子どもたちの年齢層や人数は主催者と相談の上、講師が決定できる。
ぼくのサブジェクトは「フィギュア・シアター」で、人形や仮面、影絵や自分たちの身体を総合的に使っての芝居づくり。
小学生から中学生まで三十人近い応募があり、一週間、ドタバタと楽しく過ごした
実際にどんなことをしたか、簡単に書いてみたい。
まず、サブジェクトを三つのカリキュラムに分けた。
その一。毎日始めにボディ・エクササイズをする。
これはロシアのマイケル・チェホフが創案した俳優修行の訓練を、
ぼくが子ども用にアレンジしたもの。
チェホフのオリジナルには、例えば皮膚感覚や空間認識を鋭敏にするために、自分の身体のまわりがぜんぶ粘土でできていて、腕や足、身体全体を動かすことで空間を「彫る」、そして美しい彫刻を作る、というエクササイズがある。これは小学生にはなかなか難しいもので、かなりの身体的想像力が要求される。ただし、チェホフ自身が繰り返し書いているが、「マイムのトレイニングではないので、他人からどう見えるかはまったく重要ではない。自分がどう感じられるかがすべてだ。そして大切なことは焦らないこと」である。
普段とはちがった感覚で身体を動かすためのエクササイズとして、ぼく自身は例えば次のようなゲームを子どもたちにやってもらう。参加者の中から誰か一人を選び、その子にごく単純な動作の繰り返しと、それに見合った奇妙な「音」を、これも繰り返し発してもらう。
例えばAくんが両腕を前に突き出してスクワットし、しゃがみこむたびに「ボヨヨン」という声を出す。さてそれを見て何か面白い動きなり音なりをひらめいた者が二番手となってAくんに連結してゆく。三番手、四番手と次々連なって行って、最後には奇妙で騒々しい、大きな機械ができあがる。
自分が単純な運動体となって他者のインスピレイションに「つながる」という訓練なのだが、必ずしも直接手をつないだり、身体に触れる必要はない。
子どもたちによく見られる実例で云うと、Aくんがしゃがみこんだときに降りてくる手から、次のBくんが何かを受け取るような仕草をして「ボトッ」とか「ガチャン」と叫ぶ、というものがあるが、これで到達目標は充分にクリアされている。
このヘンテコな機械はさまざまなノイズを発しながら動き続けるのだが、やがてAくんからオーヴァ・ヒートし始めて、それが次々と部品に伝わり、最後には加熱の末に壊れてしまう、というエンディングになっている。
たいていは爆発してバラバラに砕け散ってしまうが、子どもたちのキャラクタによっては凍りついたように機能停止する場合もある。

「テントで人形の部品づくり」
その二。皿やフォーク、木の枝など、身のまわりのさまざまな素材を人形のカシラや、身体の部品に見立てて、色を塗ったり、簡単な衣装を着せて合体させ、人形浄瑠璃の三人遣いに挑戦する。
文楽を始めとして日本が世界に誇る人形浄瑠璃は、まず、なぜあのように統合された動きが三人の異なった遣い手によって達成され得るのか、という点で、ヨーロッパ演劇界の驚異の的であり続けている。もちろん子どもたちのキャンプで、立派な操演者を育て上げようというわけではない。
しかし、例えば中心となる主遣いの呼吸や動きをあとの二人がサインとしてきっちり感じ取れること、また子どもたちの中で歌ったり、楽器を扱えるものが何人かいれば、太夫や三味線のように、そのメロディやリズムを道しるべに人形を動かしてみる、という工夫も生まれる。
共同でモノの動きを創り出す、というところがポイントだ。
あるグループは、たて笛を人形の胴体に見立てて、自らの音色で腕や足などを呼び集め、くっつけて歩き出す、というコンセプトだった。また、三人遣いならぬ四人遣いや五人遣いのグループも登場し、さまざまな工夫に舌を巻いた。
2005年5月号 チェコ人の人形劇意識
[2007.01.05] [「児童演劇」原稿]
チェコ人の演劇・人形劇に対する意識が、
他国と比較してもかなり高いのではないだろうか、と考える理由。
それを理解してもらうためには、ヨーロッパ大陸の真ん中にある
この小さな国の歴史を多少ひもとく必要がある。
チェコ人形劇の起源は、他の国々と同様に原始の宗教儀式にまで遡ってしまうが、
「劇人形」としての技術的基礎は、オランダやイタリア、ドイツなどの
旅芸人が持ち込んだ人形芝居が根付き、工夫されたものと云われている。
十八世紀から十九世紀にかけて強大なオーストリア・ハンガリー帝国の支配を
受けていた時代には、都市部や公的な場ではドイツ語の使用が強制された。
しかし人形劇や田舎廻りのドサ芝居ではチェコ語が認められており、
旅芸人たちは当時プラハで流行っていた話題、ファッションや政治について
面白おかしく芝居仕立てにして、地方の民衆に披露していた、と云われる。
結果としてそれがチェコ語を守る、ひいてはチェコ人としてのアイデンティティーを
守ることに結びついた。
第二次大戦後、またまた強大なソ連の指導のもと、社会主義がスタートすると同時に、
優れたアマチュア人形劇団が次々と国有化され、人形遣いは国家公務員、
芝居作りも税金で予算化される、というある意味での黄金時代が始まる。
しかし国が奨励する芸術として予算をもらって、次々と創作する中、
芸術家たちはおよそ考えつく限りの人形を使ったファンタジー、
技術的バリエーションをやり尽くしてしまったと云う。
世界中の民話や伝説を、ありとあらゆる舞台トリックで劇化し倒した、という感じか。
そうやって仕事がマンネリ化していったとき、なんとかこの状況を打破しなければ、
芸術の一ジャンルとしての人形劇が死んでしまう、何よりも社会主義がどんどんダメになって、
国の財政が落ちてきて、お客さんの数も減って、さあいよいよ革命だよ、という時期に、
もうとにかく何か新しいジャンルを創造しなければ自分たちが食いっぱぐれてしまう、という
危機感のなかで生まれたのが「フィギュアシアター」という作劇概念だった。
彼らは、オブジェとか等身大の木彫りの人形とか、どう見てもパペットや
マリオネットとは呼べないようなモノが舞台に登場する芝居をつくりはじめた。
フィギュア(形態、形象)シアターとは、ようするに開かれた人形劇、人間も出るし、
人形も出るし、モノも出るし、仮面も出るし、どんなジャンルともクロスオーヴァできる、
形あるものの舞台ということで考えられた呼び名だった。
ぼくは二〇〇〇年から二〇〇一年にかけて、日本の国際交流基金と
チェコの劇団ドラックが共同制作した「モル・ナ・ティ・ヴァシェ・ロディ!=ロミオとジュリエット」という作品に、プロデュース、共同演出として参加した。
登場する人形は等身大に近いロミオとジュリエットの二体のみ。

「モル・ナ・ティ・ヴァシェ・ロディ!=ロミオとジュリエットより」
この作品でぼくと演出のヨセフ・クロフタ(劇団ドラックの芸術監督であり、
チェコ国立芸術アカデミーの教授でもある)が試みたのは、
文楽をはじめとして日本の古典人形浄瑠璃が世界に誇る「三人遣い」、
つまり、一体の人形を三人の遣い手が背後から操る、という手法の現代的アプローチだった。
簡単に説明する。
ロミオの人形の背後で彼を操ろうとする三人の俳優はモンタギュー家の一族、
ジュリエットの背後には三人のキャピュレット家の人々。
いずれも自分たちの息子や娘を思い通りに「操ろう」とするのだが、
愛し合う二体の人形、ロミオとジュリエットは誰からも操られることを嫌い、
やがて二人きりで心中してしまう。操作者から逃れた、
あるいは操作者を失った人形、彼らはラストシーンで舞台中央に横たわり「完全な死」を
表現することになる。これが作品の基本コンセプトだった。
人形操作も役者としての演技も要求されるため、この作品には日本とチェコの頭も
身体も柔らかい若手俳優たちを中心に起用し、ヨーロッパ・ツアーを展開、
多くの街で若者たちの絶賛を浴びた。
「操るもの」と「操られるもの」。ときにはその逆転(ぼくが以前に出演した芝居には、
自分たちが舞台上で組み立てた偶像に自分たち自身が支配され、やがて奴隷になってしまう、
というものがあった)。ここにぼくはチェコの人々が持っている基本的な思想、
というか体質みたいなものを感じる。
長い歴史の中で何度も大きな国に蹂躙され、支配され続けたチェコ。
しかしそのたびに人々は劇場に集い、自分たちの境遇を笑い、
為政者が掲げるスローガンを笑い、
「真実」と呼ばれるものの多面性に気づいてきたのではないだろうか。
つづく
悩みに向き合う勇気〜チェコ人形劇の知恵、その2
[2006.11.03] [「児童演劇」原稿]
先月号から日本のテレビ番組出演について書いている。
札幌の出身小学校で、ハードな現代に生きるこどもたちのために、
チェコで十四年かけて学んだ人形劇の「知恵」を、
サヴァイヴァル・ヒントとして手渡そう、という企画。

沢のワークショップに取り組む日本のこどもたち
収録日、一日目の授業では、「変身」をテーマに身近な素材に取り組んだ。
犬だったはずのスポンジ人形がひっくり返ってヒトになる。
閉じていた傘を開くと大きな鳥になる…モノを見る目と感覚をより自由に、
柔軟に変えてゆくためのステップだ。
さて、二日目は、実際にその「柔軟な視点」がどうやって
「生きる力」になり得るのか、という応用編。
こどもたち一人一人が今、抱えている一番大きな「悩み」を
テーマに短い作品を作る、という課題に取り組んだ。
「いつもいっしょに遊んでくれた父親が単身赴任でいなくなった。
今、自分は淋しくて仕方ない、友人もいない」
「自分は目立ちたがり屋でみんなから浮いている。でも性格は変えられない」
「人前で話せない。引っ込み思案の自分が大嫌い」
今回ぼくらに与えられた六年生のこどもたちは、想像をはるかに超えて素直で誠実だった。
彼らひとりひとりが、けっして逃げずに一番つらい悩みを表明してくれたのだ。
中には「いま、このことが母さんにバレるとたいへんな家庭問題になります、勘弁してください」と言う子もいたが、それでもその内容をぼくには個人的に告げてくれた。
その勇気に泣きそうになる…。
正直書くと、そもそもたった二日間で「チェコの知恵」や「生きるヒント」などという
大それた概念を伝えきれるとも、彼らが把握しきれるとも思っていなかった。
その上、実際のところ二日目は、三十一本の一人芝居制作という物理的ストレスもかかってくる…。
二日間の苦闘、長丁場の授業が、編集作業で三十分に圧縮され、
どこまでこどもたちの心の軌跡が描ききれているのか、期待とともに不安もあるのだが、
プロデューサや監督をはじめ、ひとり残らず献身的なスタッフに恵まれたことが
すでに何かを約束してくれている、という感じはする。
そして講師本人のアホさ加減はきっと笑えると思う。
どうか楽しんで見てください。
何かに行き詰まると簡単に「むかついて」「ぶち切れ」てしまう世の中の流れに
背を向ける強さを、その力が自分自身の中にあるということを、
こどもたちは気づいてくれたのではないか、とひそかに期待している。
番組の企画立ち上げ段階で、スタッフからこんな質問があった。
「沢さんの悩み、今までにあった大きな挫折について聞かせてほしい。
どんな事に悩み、その活路をどうやって切り開いたのか、沢さん一個人のこども時代からの生い立ちが知りたい」
ぼく自身は小学生時代、困ったときにはとにかく他人と違う解法を使おう、と考える
ちょっと変わった子どもだった。
図画の時間に、白一色の雪景色ではつまらないので色とりどりの影をつけてしまう、みたいな。
そして学期ごとの学習発表会やお楽しみ会では、仲間を集めて必ず人形劇を演じた。
いつもはそれほど目立たないのに、ある季節になると現れる人形劇演出家…
じゅうぶん変わったこどもだったのではないだろうか。
六年生のとき、ふと、いわゆる「一流」になるためには二つの道がある、と気づいた。
ひとつは誰かがすでに拓いた道を、今までの誰よりも上手に歩くこと。
もうひとつは、誰も気づかなかった道を初めて拓くこと。
この場合、拓き方が上手か下手か、は問われない。
重要なのは技術ではなく、発想だ。
自分は躊躇なく後者を、そして人形劇を拓こうと決めた。
来月号、番組出演から微妙に逸れながら、続きます。
(※課外授業ようこそ先輩 番組は2006年8月に放送されました。原稿は放送前に掲載されたものです。)
心の変身術〜チェコ人形劇の知恵
[2006.11.03] [「児童演劇」原稿]
自分の出身小学校でこどもたちのために専門を生かした授業をする、
という日本のテレビ番組収録のために、懐かしい札幌の母校を訪ねた。
かつて暴れまわった教室や廊下を見たら感動して泣いてしまうのではないか、
とひそかに期待したのだが、あいにく新校舎建築のために
全面取り壊し作業の真っ最中、生徒たちはプレハブで授業を受けていた。
ただ、当時の体育館だけはそのままで、番組の多くの部分もスペースの都合から
そこで収録することになった。
出演は、ひとことで言うと「めちゃめちゃたいへんな仕事」だった。
ぼくは人形劇づくりを職業としているし、日本では中学、高校、
チェコでも大学で教師をしてきた。
だから、こどもたちに劇づくりの面白さや苦労を伝える作業を
それほどむずかしいとは考えていなかった。
最終日に感極まって号泣した講師や、
スタッフとの打ち合わせが百時間を越えた某有名作家、
収録の休憩時間に「ちくしょう、こんなはずじゃなかった」なんて
校庭の隅でいじけたアーティストなどの噂を耳にしても、
何をおおげさな、ぐらいに受け止めていたのだ。
では何がそんなにたいへんだったのか?
それはこどもたちに伝えるべきテーマが「人形劇の楽しさ」や
「演じるむずかしさ」といったわかりやすい直球ではなく、
沢則行が十四年かけて学んだチェコ人形劇の「知恵」を、
現代の日本に生きるこどもたちに生きる力、ヒントとして手渡そう、という
深くてメタな変化球だったことによる。
それではチェコ人形劇の知恵とは何か?
以下は昨年の五月号からの抜粋。
「…十八世紀から十九世紀にかけて強大なオーストリア・ハンガリー帝国の支配を
受けていた時代には、都市部や公的な場ではドイツ語の使用が強制された。
しかし人形劇や田舎廻りのドサ芝居ではチェコ語が認められており、
旅芸人たちは当時プラハで流行っていた話題、ファッションや政治について
面白おかしく芝居仕立てにして、地方の民衆に披露していた、と云われる。
結果としてそれがチェコ語を守る、ひいてはチェコ人としての
アイデンティティーを守ることに結びついた…
長い歴史の中で何度も大きな国に蹂躙され、支配され続けたチェコ。
しかしそのたびに人々は劇場に集い、自分たちの境遇を笑い、
為政者が掲げるスローガンを笑い、『真実』と呼ばれるものの多面性に
気づいてきたのではないだろうか…」
誤解されるのを覚悟の上でかなり乱暴な言い方をすると、
こうしなければならない、あるいはこうでなければ生きてゆけない、という
狭さく状況に人間が陥ったとき、いやあ、こっちでもいいんじゃない?とか、
別な道でも生きて行けるよ、といったある種の「逃げ道」を見つける
命がけのユーモアとサヴァイヴァル技術こそ、演劇、人形劇を通しての
チェコ人の「知恵」と言えるものだと思う。
それは自分の立場や視点を硬直させずに、できるだけ心を柔らかく保つ、
一本しか見えない正解への川筋のそばで、別の運河を掘り始める、という作業でもある。

収録日、一日目の授業では、まず自分の小作品のいくつかをこどもたちに観てもらった。
ぼくには、魚のからだが分解したり反転したりすることで仮面や蝶に変わる、
傘が変形して生き物になる、といったヘンテコな芝居がいくつかある。
それらのサンプル上演の後、座布団大のスポンジや百円ショップの傘をこどもたちに渡し、
ちょっと見方を変えるだけでそれらが別なものに変身する、
そんなプロセスを見つけてほしい、という課題を出した。
たとえばうまく歩けない四角なスポンジが、半分にちぎれることで二枚の翼になって
空高く舞い上がる、とか、雨よけの傘を元気良く開くと美しい花火になっている、とか、
ようするに物体に対する視点の切り替え、簡単な工作によるあっと驚く変形、
といったテーマだ。結果として、こどもたちは大人がとても思いつけないような、
実に奇抜な「変身」をいくつも見せてくれた。
この報告、来月号に続きます。